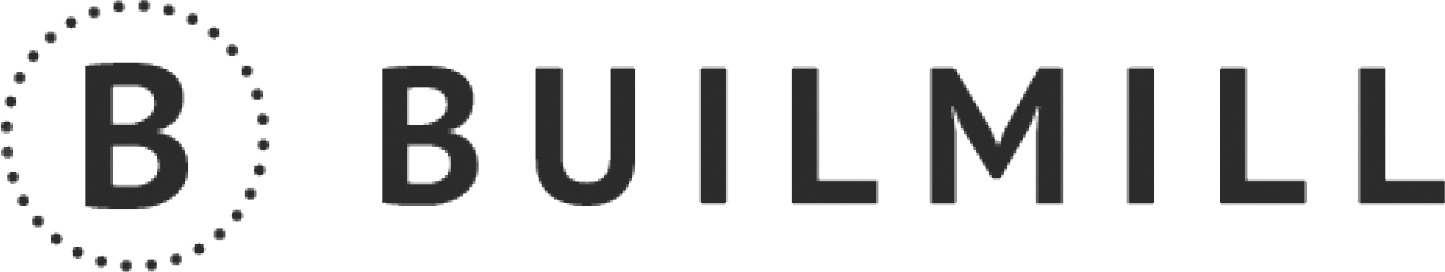概要:オフィスの賃貸契約では、登記簿面積と実際の使用可能な面積が異なることがあります。本記事では、登記簿面積の定義と、実際のオフィス面積との違いについて解説します。契約時に注意すべきポイントや、面積の確認方法についても紹介します。
はじめに

オフィスの移転を検討する際には、登記簿面積と実際に使用できるオフィス面積の違いについて理解しておくことが重要です。この違いを把握することで、賃貸契約時に想定外のトラブルを避け、計画通りのオフィス空間を確保することが可能になります。また、面積の相違を知ることで、内装計画もスムーズに進めることができ、企業のニーズに合ったオフィス環境の実現に繋がります。
本記事では、登記簿面積の基本的な定義と、実際に使用可能なオフィス面積との違いについて、わかりやすく解説します。オフィス移転や賃貸契約を行う際に役立つ基礎知識としてぜひご参考ください。
登記簿面積とは
概要
登記簿面積とは、建物が法的に記録されている面積のことです。この面積は、法務局で管理されており、建物の所有権や区分所有法に基づいて登記されるため、法的な裏付けがあります。登記簿面積には共有部分が含まれることが多く、実際の使用可能面積と異なるケースがあります。
登記簿面積と実際のオフィス面積の違い
登記簿面積には、廊下やエレベーター、ロビーなどの共有部分が含まれていることが多いため、必ずしも企業が実際に利用できる面積を表しているわけではありません。
- 実際のオフィス面積は、これらの共有部分を除いた面積であり、企業が日々の業務で使用できるスペースを指します。
- このため、登記簿面積と実際の使用可能面積に差が生じることが一般的です。
契約時の注意点
オフィスの賃貸契約を行う際には、登記簿面積と実際に使用可能な面積の両方を確認することが重要です。これにより、賃料がどの面積を基準にして設定されているかを明確にし、契約後の誤解やトラブルを防ぐことができます。
- 賃貸契約の際に提示される面積が登記簿面積である場合、実際に利用できる面積がその分狭くなることを念頭に置きましょう。
- また、内装計画を立てる際には、実際のオフィス面積に基づいてプランニングすることが大切です。共有部分が含まれていない、実際に使用可能な面積に基づくことで、より正確で現実的な内装計画が可能になります。
登記簿面積を理解することで、オフィスの選定や内装のプランニングがよりスムーズになり、企業にとって最適なオフィス環境の確保につながります。
まとめ
オフィス移転を成功させるためには、登記簿面積と実際のオフィス面積の違いを理解し、賃貸契約の際にしっかりと確認しておくことが非常に重要です。この確認を怠ると、思わぬトラブルが生じたり、内装計画に支障が出たりする可能性があります。事前に登記簿面積と実際の利用可能な面積を確認することで、計画通りに内装を進め、企業のニーズに合ったオフィス空間を確保することができます。
納得のいくオフィス移転を実現するためには、登記簿面積とオフィス面積の基本知識を押さえておくことが不可欠です。これにより、内装計画を円滑に進めるだけでなく、企業にとって最適なオフィス環境の整備が可能になります。オフィス選びの際には、今回の基礎知識を参考にし、慎重に確認作業を行いましょう。